
ブラジルにコーヒーの木がもたらされたのは18世紀前半のこと。
当時、ブラジルの主力産業は砂糖の生産でしたが、その後、国際情勢の変化の中でこれをコーヒーに大転換。
20世紀の初頭には世界のコーヒー生産のおよそ80%までを担うようになっていました。
労働人口の約90%がコーヒー産業に従事し、外貨収入の約90%をコーヒーに依存していました。
ブラジルなくしてはコーヒーは語れず、コーヒーなくしてはブラジルは語れなかったといえるでしょう。
まさに当時のブラジルは「世界のコーヒーカップ」だったのです。
しかしながら、こうした単一の産品に過度に依存する経済は、市場経済のシステムの中では大きな危険をはらんでいます。
というのも、受給のバランスが価格を決定する市場経済では、価格が生産者の意志とは無関係に変動するからです。
本来歓迎されるはずの豊作が、産品の著しい価格下落を招いてしまう場合もあります。
そのようなことになれば、国家経済の危機です。
こうした経済構造は、一般に「モノカルチャー経済」と呼ばれています。
植民地化された経験を持つ国によく見られる事例で、多くの国が独立を果たしたのちも、そこから脱却することができないでいました。
ブラジルも例外ではありませんでした。

そんなブラジルは1906年、コーヒーの大豊作に見舞われます。
ブラジル政府はこの事態に際し、外国からの借款に頼ってまで、自国のコーヒーを買い上げました。
このコーヒーが市場に出回れば、価格の大暴落は必至です。
コーヒーに依存するブラジル経済は破綻を免れないでしょう。
各地の倉庫には800万袋とも、1000万袋ともいわれるコーヒーが山積みになったそうです。
価格の暴落を回避するためには、これを少しずつ市場に出すしか手はありません。
ただ、事態はそれだけでは収まらなかったのです。
というのも、いったん収穫樹齢に達したコーヒーは、その後30年から40年は毎年実を結びます。
そのため、たとえ1906年のクロップを処分できたとしても、それに匹敵するニュークロップが翌年も、翌々年も収穫されてしまうのです。
結果、ブラジルが在庫のコーヒーをすべて処分できたのは、1913年のことでした。
じつに余剰コーヒーの処分するのに7年の歳月を要したわけです。
きわどいところでの危機回避でした。しかし、そんなブラジルをその翌年、さらなる苦難が待ち受けていました――。
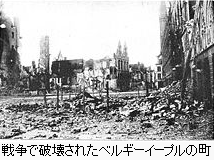
1914年6月28日、ボスニアを視察に訪れたオーストリア・ハンガリー帝国の皇太子、フェルディナント大公をセルビア人青年が暗殺。
オーストリア・ハンガリー帝国は、セルビア政府に宣戦布告し、これがヨーロッパ全土を巻き込んだ戦争へと発展していきます。
第1次世界大戦の勃発です。
ヨーロッパ各国のコーヒー需要は著しく低下し、豊作による危機をなんとか脱したブラジルを直撃しました。
戦争が終結したとしても、ヨーロッパ諸国の疲弊は長くあとを曳くことになるでしょう。
もはやコーヒー立国ブラジルの命脈は風前の灯火でした。

ところが1919年、ブラジルは信じられない幸運に恵まれます。
ヨーロッパ以外ではブラジルコーヒーの受け皿となる可能性を持った唯一の国、アメリカで後世に長く語られることになる法律が施行されたのです。
「酒類製造・販売・運搬等禁止法」、いわゆる「禁酒法」です。
法律で酒を禁止されたアメリカでは、一気にコーヒーの需要が高まりました。
その結果、ブラジルは戦争で疲弊したヨーロッパに変わる輸出先を得、そればかりか年来の在庫まで一掃することに成功したのです。
こうして瀬戸際まで追いつめられたブラジルは、世紀の悪法として知られる、アメリカの「禁酒法」によって息を吹き返すことになります。
 コーヒーのはなし
コーヒーのはなし